家の壁を歩いている小さな生き物を見て、「あれってトカゲ?ヤモリ?それともイモリ?」と迷ったことはありませんか?
名前や姿が似ているトカゲ・ヤモリ・イモリですが、実はそれぞれ異なる特徴を持っています。
この記事では、トカゲヤモリ 違いを中心に、見分け方・生態・分類の違いをわかりやすく解説。
また、イモリとヤモリの違い 覚え方や、トカゲ ヤモリ 違い イラストの視覚的な理解ポイント、カナヘビとの違いについても触れていきます。
これから彼らを飼育したい方や、身近な自然に関心を持ち始めた方の参考になれば幸いです。
この記事を読むと、以下のことが理解できます:
- トカゲとヤモリの見た目や行動の違い
- イモリとヤモリの分類と生態の違い
- 覚えやすい見分け方のコツ
- トカゲ・ヤモリ・カナヘビの見分け方
トカゲヤモリ 違いの基本を解説
イモリとヤモリの違い 覚え方

イモリとヤモリの違いを覚える最も簡単な方法は、「住む場所と漢字」です。
- イモリ(井守):水辺に住む両生類。
- ヤモリ(家守):家の壁など陸に住む爬虫類。
このように、漢字を覚えることで生態の違いが自然に頭に入ってきます。
また、お腹が赤いのがイモリという視覚的な特徴も重要です。これはイモリが毒を持っていることを示す警戒色です。
イモリは川や池などの水辺に生息しており、皮膚はしっとりと湿っています。これは水中でも生活できる両生類ならではの特徴です。
一方、ヤモリは乾いた皮膚をもち、陸上で生活する爬虫類です。足の裏には「趾下薄板(しかはくばん)」と呼ばれる吸盤状の構造があり、壁やガラス面を自在に移動することができます。
夜間、家の壁や窓に張り付いている小さな生き物を見かけたら、それはヤモリである可能性が高いでしょう。
トカゲとヤモリは手も全然違う!
トカゲとヤモリの手や足の構造には大きな違いがあります。
ヤモリの足には、粘着力のある細かい構造が備わっており、これが垂直の壁や天井を登る力の源になっています。これに対して、トカゲの足には吸盤はなく、発達した爪によって地面を掴みながら移動します。
また、目元にも注目してみましょう。ヤモリにはまぶたがなく、瞳を覆う透明な膜で目を保護しています。そのため、目を閉じることができません。トカゲはまぶたを持ち、まばたきをすることができます。見た目の印象にも大きな違いが出るポイントです。
さらに、体型にも差があります。ヤモリは比較的丸みを帯びた短めの体つきで、トカゲは細長くしなやかな体型をしています。動きにもその体型の差が表れており、トカゲは素早く地表を走る姿が印象的です。
イモリ・ヤモリ・トカゲの仲間分けって?
見た目では判別しにくいこともあるため、生物学的な分類にも注目しておきましょう。
- イモリは両生類:水中と陸上の両方で生活する動物です。皮膚は滑らかで湿っており、水辺を好みます。成長過程でエラから肺呼吸へと変化します。
- ヤモリとトカゲは爬虫類:乾いた環境に適応しており、うろこ状の皮膚で体を保護しています。呼吸は常に肺で行い、主に陸上で生活します。
この分類の違いを理解しておくことで、生態や飼育方法の違いも自然と納得できるようになります。
表で見る!トカゲとヤモリの違い

視覚的に理解するためには、特徴を一覧表にして整理するとわかりやすくなります。
| 特徴 | トカゲ | ヤモリ |
|---|---|---|
| 活動時間 | 昼行性 | 夜行性 |
| 体型 | 細長くスリム | 丸みを帯びた体型 |
| 皮膚 | 光沢のある鱗 | 灰色で柔らかい皮膚 |
| まぶた | あり | なし(例外あり) |
| 足の構造 | 爪が発達 | 吸盤(趾下薄板)あり |
| 生息場所 | 草地・森林 | 家屋の壁や窓 |
この表を頭に入れておくことで、実際に目にした時にどの生き物なのかをすぐに判断しやすくなります。
ヤモリと他の爬虫類の違いも押さえよう
ヤモリ・イモリ・トカゲ・カナヘビの違い
身近な自然の中には、ヤモリ、イモリ、トカゲ、カナヘビといった小型の生き物が多く生息しています。
名前が似ている上に見た目も似ていることから混乱しがちですが、それぞれ生態や分類がまったく異なります。
- ヤモリ:夜行性の爬虫類。足に吸盤があり、壁やガラス面を登ることができる。
- イモリ:水辺に住む両生類。毒を持ち、お腹が赤いのが特徴。
- トカゲ:昼行性の爬虫類。爪が発達し、地表を素早く移動する。
- カナヘビ:細長く、茶色い体が特徴の昼行性爬虫類。動きが俊敏。
それぞれの違いを理解しておくことで、自然観察がより楽しくなるでしょう。
ヤモリとカナヘビはここが違う!
ヤモリとカナヘビは、体の色や行動パターンで見分けがつきます。
- 活動時間の違い:ヤモリは夜行性で夜に活発。カナヘビは昼間に活動する。
- 皮膚の質感:ヤモリは灰色でもちもちした皮膚。カナヘビは茶色でザラついた皮膚。
- 目の形:ヤモリの目は縦長の瞳孔、カナヘビは黒目が丸く目立つ。
- 登る力:ヤモリは吸盤で壁やガラス面も登れる。カナヘビは爪で登るが、垂直面は苦手。
このように行動や外見で見分けることが可能です。
どこで見かける?出現場所で見分けるコツ
出会う場所によって、どの生き物かを推測する手がかりにもなります。
- ヤモリ:夜間、住宅の外壁や窓、街灯の下などでよく見かける。
- トカゲ・カナヘビ:昼間、日当たりの良い草むら、石垣、公園などに出現。
日中に太陽の下で日光浴しているのはトカゲかカナヘビ、夜に光に集まる虫を狙っているのがヤモリという見分け方もできます。
飼育方法にもこんな違いがある!
それぞれの種類は飼育方法にも明確な違いがあります。
- イモリ:水槽と水環境が必要。再生能力が高く、比較的飼いやすい。
- ヤモリ:乾燥を保った陸上環境。ケースの蓋は脱走防止のため必須。
- トカゲ・カナヘビ:日光や紫外線、温度管理が必要。活発な動きをするため広いスペースが理想。
飼育を考える場合は、必要な設備や知識をあらかじめ確認しておきましょう。
トカゲにもいろいろな種類がいる
日本国内でよく見られるトカゲの種類には、以下のようなものがあります。
- ニホントカゲ:成体は茶色、幼体のしっぽは鮮やかな青色。光沢のある体表が特徴。
- カナヘビ:体全体が茶色く、体長の半分以上をしっぽが占める。素早い動きが特徴。
触れたときの質感も異なり、ヤモリはぷにぷにと柔らかく、トカゲやカナヘビはしっかりとした鱗の感触があります。
観察時には、色・動き・生息場所など複数の要素を総合して見分けることが大切です。
トカゲヤモリ 違いのまとめ
- トカゲは昼行性、ヤモリは夜行性
- ヤモリには吸盤(趾下薄板)があるが、トカゲにはない
- イモリは両生類で、お腹が赤く、水辺に生息
- ヤモリはまぶたがなく、トカゲにはまぶたがある
- カナヘビは茶色く細身、ヤモリは灰色で丸みがある
- イモリは毒を持ち、お腹の赤さが特徴
- 出現時間と場所である程度判別できる
- ヤモリは家の壁や天井、トカゲは草むらで出現
- トカゲとヤモリはどちらも爬虫類だが属する科が異なる
- ヤモリの目は縦長の瞳孔で夜行性に適応
- イモリは皮膚がしっとり、ヤモリとトカゲは乾燥した鱗状皮膚
- 飼育時の環境にも明確な違いがある
- ヤモリは害虫駆除に役立つ益獣
- カナヘビには吸盤がなく、壁を登れない
- イモリとヤモリは漢字の意味から違いを覚えやすい






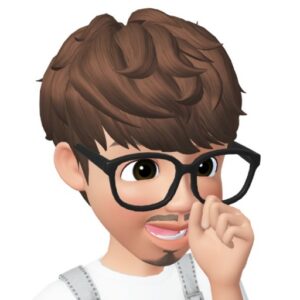
参考になった方は、ぜひコメントを!